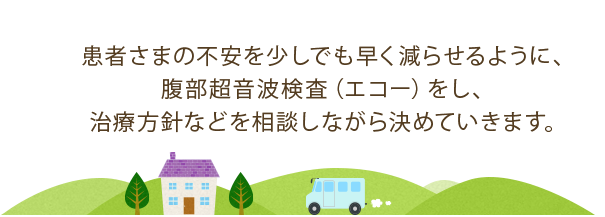消化器肝臓科
診療内容
胃潰瘍・十二指腸潰瘍、慢性胃炎、逆流性食道炎、ヘリコバクターピロリ感染症、腹痛、下痢、肝機能障害、B・C型慢性肝炎、肝硬変、アルコール性肝障害、胆石症など。
主な症状について
胃潰瘍
胃潰瘍は、胃酸(食べ物を粥状に消化するために分泌)がなんらかの原因によって胃粘膜まで消化してしまい、胃壁がただれて傷つき、ひどいときには筋肉までえぐりとってしまった状態です。
症状の三大特徴は、痛み、過酸症状、出血といわれます。
治癒と再発をくり返す潰瘍は、ピロリ菌感染による影響も指摘されています。
十二指腸潰瘍
ピロリ菌、非ステロイド性抗炎症薬などにより、粘膜が傷つき、そこが胃液の攻撃にさらされることで、胃や十二指腸の粘膜や組織の一部がなくなる病気です。
慢性胃炎
慢性胃炎は、胃粘膜の状態によって、胃粘膜表面で軽い炎症のある状態や、炎症により胃粘膜表面がえぐれた状態、胃粘膜表面が正常より厚く見える状態と分けられます。そのうち一番多いのは萎縮性胃炎といって、胃粘膜の炎症が長く続いたために胃粘膜自体が萎縮し薄くなっている状態の慢性胃炎です。
逆流性食道炎
強い酸性の胃液や、胃で消化される途中の食物が食道に逆流して、そこにとどまるために、食道が炎症を起こし、胸やけや胸の痛みなどさまざまな症状が生じる病気です。
腹部超音波検査(エコー)
- ■腹部超音波検査(エコー)とは?
- 高い周波数の音波を利用して、コンピューター処理で画像化し診断します。
X線検査のように放射線被爆の心配がなく、患者様の苦痛もなく安全な検査です。
- ■何がわかるの?
- 主に、肝臓、胆嚢、胆管、膵臓、腎臓、脾臓、膀胱などの観察を行います。
検診・ドックにて肝機能障害、脂肪肝、肝腫瘍、胆石、胆嚢ポリープなどを指摘された方の二次検診、フォローアップ、慢性肝炎、肝硬変、肝臓癌、膵臓癌、腎臓癌などのチェックに適しています。
- ■どのように行なうの?
- 腹部を広く出し、検査台に仰向けになり、両手を頭の方にあげます。
腹部にゼリーを塗って探触子(プローブ)を押し当て、腹部内臓器の断面層の画像をモニターテレビで観察します。
- ■検査を受けるときの注意
- 基本的に腹部内に空気が多く存在すると、画像がよく見えません。
食後は消化管内空気が発生しやすいため、絶食の状態で行います。
膀胱を検査する場合は、尿がたまっているほうが詳しく観察できるので、検査前の排尿は我慢するようにします。
- ■検査について(腹部超音波検査(エコー)ご希望の方へ)
- 検査当日、朝食は食べずにご来院ください。
水分はコップ1杯(250ml程度の水・お茶(砂糖・ミルクは入れない)のみ)なら可。
当日朝の薬は飲まないでください。
検査前日の食事は22時頃までとし、内服薬は服用してかまいません。
ご予約は特に必要ありませんので、通常の外来診療時間内にご来院をお願い致します。